トップメッセージ
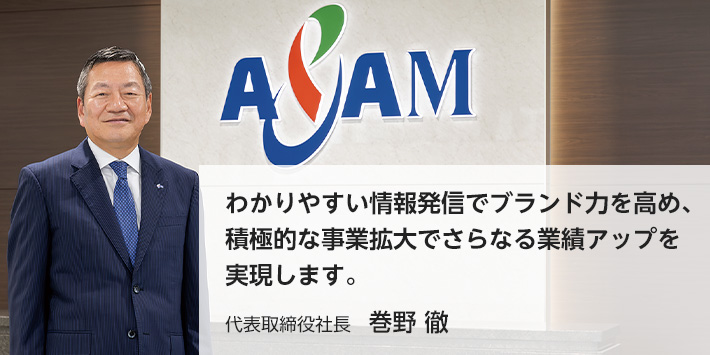
企業価値と業界優位性を伝えるブランド強化に向けて
株主をはじめステークホルダーの皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年、統合報告書を初めて発刊して以来、お取引先など当社と縁の深い方々とお会いするたびにご感想やご質問をいただけることが増えてきました。これまでの決算短信や有価証券報告書などの財務情報では伝えきれない人材や技術力、知的財産、環境、価値創造ストーリーなどを含めて当社グループを知っていただくことで、皆様との親密さや相互理解が深まったと実感しています。
また、ステークホルダーの皆様とより円滑なコミュニケーションが図れるよう、2025年2月に本社を全国からアクセスがよい品川駅近隣に移転しました。さらに、当社グループの活動や技術をリアルタイムで多くの方々に知っていただけるようSNS(Instagram)も始めています。当社グループは、他社の追従を許さない優れた技術・商品・サービスを備えており、その多くが建設・建材、産業インフラなどの分野で強みを発揮しています。長期経営構想「Vision2033」では、当社の強みを最大限活かす投資と事業展開を段階的に進め、売上高1,000億円の企業グループに成長する未来を描いています。
事業拡大に向け、投資を進めた「2026中期経営計画」初年度
その1st Stageとなる「挑戦と変革」が走りだした2024年度は、建設・建材事業における販売価格の改定、工業製品・エンジニアリング事業の大型工事の完成により、売上高は増収となりました。一方、利益面では原燃料の高騰、外注労務費・物流費の増加などの外部要因に加え、M&Aや本社移転、従業員の働き方改革、採用・ブランド強化など中長期を見据えた成長投資が大きく影響し、営業利益、経常利益は減益となりました。2024年度は、1st Stage「挑戦と変革」に掲げる売上高500億円の達成に向けて事業拡大を目的とした投資を優先しており、その種まきを進めた1年だったと考えています。
大きな進展として、M&Aにより既存・新規の双方にまたがる事業拡大の基盤ができたことが挙げられます。2024年10月に建材・家具などに使用される低圧メラミン化粧板を製造・販売する大昭和ユニボード㈱、続いて2025年4月には高意匠性・高機能性の化粧紙・フィルムの印刷技術を有するDICデコール㈱を子会社化し、それぞれユニボード㈱、デコール㈱に社名変更しました。この2社の技術に、当社が今まで培ってきた熱をコントロールする技術が活かされている耐火性に優れた不燃ボードを組み合わせることで、これまでにない高付加価値建材の開発・生産・販売までの一貫体制が構築できます。すでに3社の営業が集まって販路開拓に向け連携を深めており、工場の生産設備が整い次第始動する予定です。
さらに、発電所や各プラントに供給している国内シェアNo.1の非金属製伸縮継手「APコネクター」では、オーダーメイドが中心ということもあり、顧客に寄り添った「アフターフォローを充実させた制度」の整備に注力しました。これによって、顧客との関係性を深め、新たな受注獲得や継続した受注につなげる営業体制の強化も進めています。
国内造船業の活況を追い風に船舶分野でビジネスモデルを確立
2026中期経営計画では「ビジネスモデル発想による新価値創造」を基本方針の一つに掲げ、新たな販路を船舶分野で拡大しています。工業製品分野では、国内の新造船建造の回復に合わせて自動車運搬船向けの防熱材や副資材の出荷が大幅に増加しています。エンジニアリング分野では、国内では初となる「LNG燃料のタンク保冷工法」が高く評価され、受注が増えています。この旺盛なニーズにお応えするために、技術開発研究所では保冷工事の効率化を進めているところです。また、ウクライナ危機など国際紛争で調達が難しくなった資材に代わる材料の検討にも着手しています。
船舶の内装分野でも、当社の技術が一躍注目を集めています。船舶のエンジンルーム周辺では会話ができないほどの騒音にさらされるのが常ですが、当社の製品を用いた複合材を床やドアに施工することで遮音性が飛躍的に高まり、船内業務の環境改善につながります。この施工を船員の居住エリアにも適用すべく、船舶の居住空間の基準に合致した高性能製品の開発を進めています。
アグリビジネス、温暖化対策など環境課題を解決に導く新たな挑戦

新たな事業展開として、環境領域にも広く乗り出しています。その一環としてアグリビジネスに進出しており、ウイルスや一般細菌の除去ができる散布型除菌剤「ヨドックス粒」を開発・販売しています。ヨドックス粒は、動植物への侵襲が低く、鳥インフルエンザなどの感染症拡大の抑制に効果があります。大手養鶏場で確認を進めていますが、“畜産業の衛生管理のスタンダード”となるよう動物医薬品の認定取得に向けた手続きも進めています。また、サツマイモやイチゴの活性を高める効果があることが分かり、農作物の品質向上に貢献する新しい農業資材として商品化を進めています。
スマートファクトリーからECビジネスまで新たな価値を創出するDX変革
当社グループでは、技術の継承、人手不足、コスト上昇といった製造現場の課題解決策としてスマートファクトリー化を推進しています。長期経営構想「Vision2033」では、「働き方」「生産工程」「提供価値」の3段階に分けて、スマートファクトリーへの移行を画策しており、その第1段階として、IoTを活用した「生産工程の見える化」システム、タブレット版操作マニュアルなどDXを進めました。
また、新たな販売経路として、ECビジネス事業の構築も始まっています。当社の製品を求めるお客様に最短かつ低コスト、スピーディーに製品をお届けするサービスで、建材から工業製品、ヨドックス粒などの環境製品まで多品目多品種をラインアップしていく予定です。
「人」の活躍を最大化する従業員の声を取り入れた人的資本戦略

長期経営構想「Vision2033」の成長戦略と長期CSRビジョン「CSR2033」は、当社の持続的成長を支える両輪であり、サステナブルな事業活動を通じてこれらのビジョンを実現し、働きやすい会社にしていくためには、新たな人事制度が必要だと感じました。そうした経緯から、若手中堅従業員19名を集めて「ありたい働き方実現プロジェクト」を立ち上げました。メンバーからは人事施策について経営側に提案がなされ、それを受けてこの4月から新たな人事制度がスタートしました。その柱となるのが「転勤選択制」「キャリアプラン設計」「働き方の多様化」です。本人が転勤を選択できる制度とし、育児や介護などライフステージに合わせた柔軟な働き方を可能にするものです。また、従業員のキャリアプランを設計し、それに沿った人事異動や研修を提供していきます。管理職層にはコーチング研修を実施し、従業員一人ひとりが成長を実感できる制度を整備しました。
また、同時進行で健康経営の推進にも力を入れています。昨年度「健康経営推進室」を設置し、「健康経営優良法人2025」にも初認定されました。当社とグループ会社の㈱アスクテクニカは、子育てサポート企業として「くるみん認定」も受けています。さらに、健康増進につながる福利厚生メニューを充実させ、当社グループとして従業員やその家族が健康的に安心して働き続けることができる職場づくりを進めていきます。当社グループの最大の資産はなんといっても「人」です。私は定期的に国内全拠点を回り、現場の従業員との食事交流会を行っていますが、そうした場で従業員から率直に伝えられる思いは、私に与えられた宿題であり、会社をより良くする改善のヒントだと考えています。食事をしながら従業員の言葉に耳を傾け、忘れないように箸袋の裏にメモをすることもあります。従業員がやりがいをもって仕事に取り組めることが当社グループ成長の原動力です。今後も従業員中心の人的資本戦略を充実させていきたいと考えています。
社会に価値あるビジネスモデルで時代を超えて成長し続ける
当社グループの成長戦略は、従業員が自分達の会社の実力と価値を自覚し、それを磨き続けることだと私は考えています。例えば、主要セグメントである建設・建材分野では、建築着工件数の減少に合わせて建材需要も徐々に減ってきています。当社グループも市場縮小による売上減少・利益の確保に苦しんでいましたが、営業面での意識改革に大きく舵を切りました。元々、当社グループの製品・技術・サービスは、他社に比べても高機能・高性能で、デリバリー能力も高く、強い競争力を有しています。ですから、事業運営に必要な利益を確保していくために、製品価格の引き上げを行いました。引き上げによってシェアが下がる心配もありましたが、実際にはシェアが上がる逆転現象が起こりました。その後、コロナ禍、原燃料価格や物価の高騰で足踏みした時期もありましたが、高付加価値のビジネスモデルで利益を獲得していくという当社グループの戦略は一貫して変わりません。
今後は、建設・建材事業、工場製品・エンジニアリング事業という従来の事業体制から、建設・建材、産業インフラ、環境という3つの領域に事業価値を再定義し、異分野にも積極的に挑戦していきます。また、海外事業展開を加速させるため、新たなプロジェクトチームも立ち上げました。「『エーアンドエーマテリアルグループの実力(可能性)は、まだまだこんなものじゃない。』ということをこれからも皆様にお伝えしていきたい。」私からのメッセージを含めて、この統合報告書はそんな思いで作っています。そして、一人でも多くの皆様に当社のファンになっていただけることを願っています。ステークホルダーの皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。